症状 / 上半身
動悸・息切れ
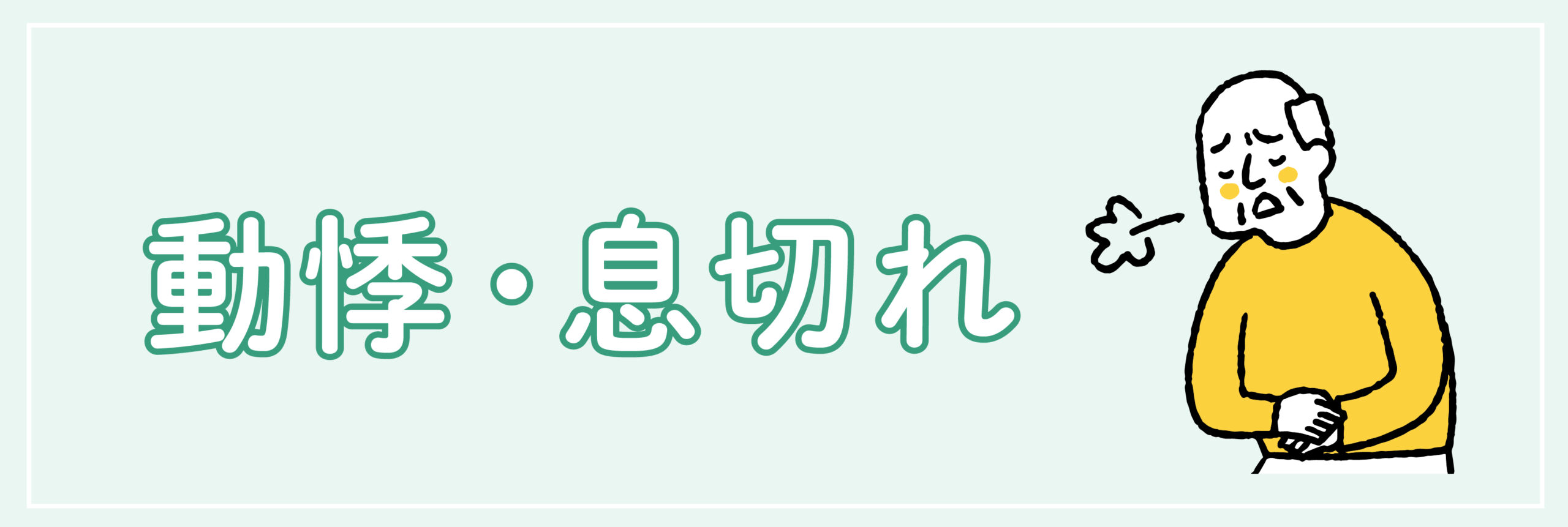
▶動悸・息切れについて
動悸とは、心臓の拍動を普段より強く感じたり、速く感じたり、あるいは脈が飛んだり乱れたりする不快な症状のことです。一方、息切れは、少し体を動かしただけで息が上がったり、呼吸が苦しく感じたりする状態を指します。これらの症状は、誰もが一度は経験する身近なものですが、単なる疲労やストレスが原因であることもあれば、心臓や肺などの重大な病気が隠れているサインであることもあります。
当クリニックでは、動悸や息切れの原因を正確に特定し、患者さまの状態に合わせた適切な診断と治療を行っています。不安を感じながら日常生活を送る必要はありません。気になる症状があれば、お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
▶動悸・息切れの原因
動悸や息切れは、非常に多くの原因で起こります。原因を特定するためには、症状の現れ方や、他にどんな症状があるかなどを詳しく調べることが重要です。主な原因としては、以下のようなものが挙げられます。
| 心臓の病気 |
|---|
| 【不整脈】 心臓のリズムが乱れる病気で、脈が速くなったり、遅くなったり、飛んだりすることで動悸を感じます。 |
| 【心不全】 心臓のポンプ機能が低下し、全身に十分な血液を送れなくなることで、息切れやむくみなどが生じます。 |
| 【狭心症・心筋梗塞】 心臓の血管が狭くなったり詰まったりすることで、胸の痛みとともに動悸や息切れを感じることがあります。 |
| 【弁膜症】 心臓の弁に異常が生じ、血液の流れが悪くなることで、動悸や息切れの原因となります。 |
| 肺や呼吸器の病気 |
| 【気管支喘息】 気道が狭くなることで、息苦しさや「ゼーゼー」といった呼吸音とともに息切れや動悸を感じます。 |
| 【慢性閉塞性肺疾患(COPD)】 主に喫煙が原因で肺の機能が低下し、徐々に息切れが悪化します。 |
| 【肺炎・気管支炎】 肺や気管に炎症が起き、咳や痰とともに息切れを伴うことがあります。 |
| 【気胸】 肺に穴が開き、突然の息切れや胸の痛みが起こります。 |
| その他の原因 |
| 【貧血】 血液中の酸素を運ぶヘモグロビンが不足することで、動悸や息切れ、だるさなどを感じます。 |
| 【甲状腺機能亢進症】 甲状腺ホルモンが過剰に分泌されることで、動悸、体重減少、発汗などの症状が現れます。 |
| 【ストレス・不安・パニック障害】 精神的な要因で、心臓がドキドキしたり、息苦しさを感じたりすることがあります。 |
| 【過労・睡眠不足】 体の疲労や睡眠不足が、一時的な動悸や息切れを引き起こすことがあります。 |
| 【薬物の副作用】 一部の薬の副作用として、動悸や息切れが起こることがあります。 |
▶検査と治療
動悸や息切れの原因を正確に診断するため、問診で症状を詳しく伺うことに加え、必要に応じて以下の検査を行います。
検査
- 心電図検査: 心臓の電気的な活動を記録し、不整脈の種類や、心臓への負担の有無などを調べます。
- 胸部X線検査(レントゲン): 肺や心臓の大きさ、形、異常影の有無などを確認します。
- 血液検査: 貧血の有無、甲状腺ホルモンの値、心臓への負担を示すマーカー、炎症反応などを調べます。
- 心臓超音波検査(心エコー): 心臓の動きや弁の状態、心臓の大きさなどを詳しく観察し、心不全や弁膜症の有無などを確認します。
- ホルター心電図検査(24時間心電図): 携帯型の心電計を装着し、日常生活中の心臓の動きを24時間記録することで、不整脈の頻度や種類を詳しく調べます。
- 呼吸機能検査: 肺の働き(肺活量や空気の出し入れの能力)を調べ、喘息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)、間質性肺炎などの呼吸器疾患の有無を確認します。
治療
検査結果に基づき、患者さまの状態や原因疾患に合わせた治療を行います。
【薬物療法】
不整脈の種類に応じた薬、心不全の薬、気管支を広げる薬、貧血の薬、甲状腺ホルモンを抑える薬などを処方します。
【生活習慣の改善指導】
ストレス軽減、十分な睡眠、禁煙、適度な運動、バランスの取れた食事など、症状を和らげ、病気の進行を防ぐためのアドバイスを行います。
【専門医療機関への紹介】
緊急性が高い場合や、より専門的な検査・手術が必要な場合には、速やかに地域の基幹病院や専門医療機関へご紹介し、連携して治療を進めます。
▶受診の目安
- 動悸や息切れが突然始まり、強い不安を伴う
- 胸の痛みや圧迫感を伴う
- 意識が遠のく感じがする、実際に意識を失ったことがある
- 冷や汗や吐き気を伴う
- 座っていても、横になっても息苦しさが改善しない
- 足のむくみがひどい、急に体重が増えた
- めまいやふらつきを伴う
- 症状が長く続く、または徐々に悪化している
- 過去に心臓病や肺の病気を指摘されたことがある
※本ページの内容は、みらいとクリニックの医師が監修しています。
