症状 / 上半身
吐き気/嘔吐
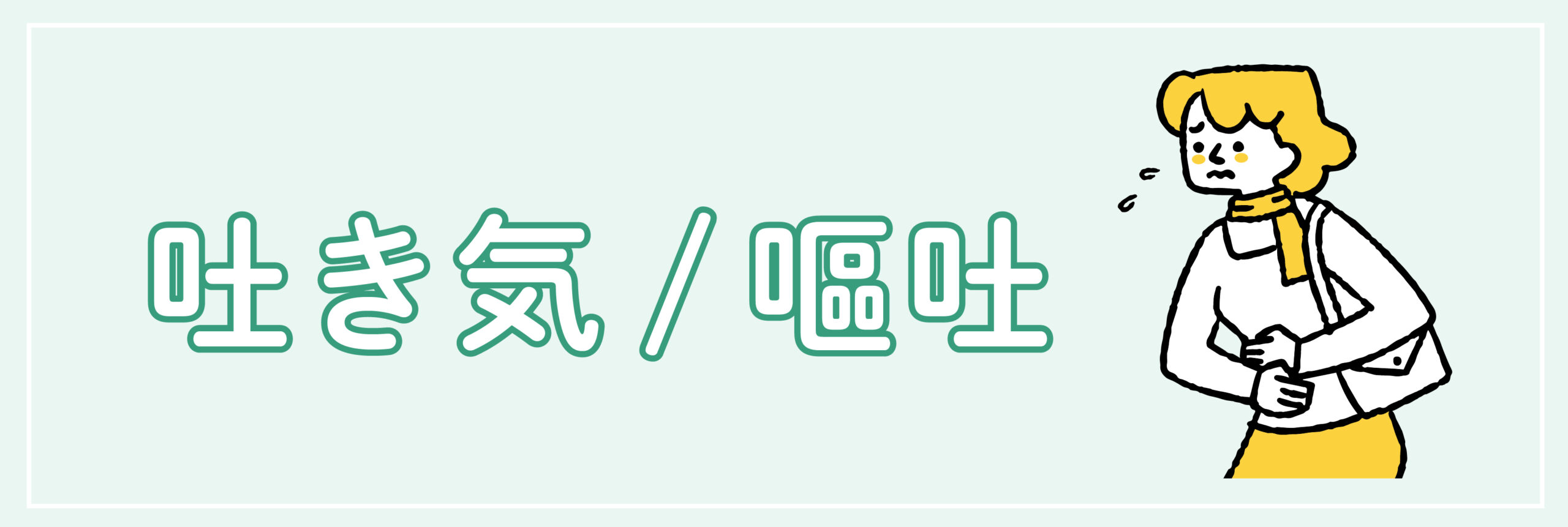
▶吐き気/嘔吐について
吐き気(悪心)は「気持ちが悪い」「むかむかする」といった不快な感覚で、嘔吐は胃の内容物を口から吐き出すことです。これらの症状は、私たちの体にとって非常に身近なもので、食あたりや乗り物酔い、ストレスなど、一時的な原因で起こることがほとんどです。しかし、中には消化器系の病気だけでなく、脳の病気や心臓の病気、あるいは全身の病気など、さまざまな原因が隠れている場合があります。
当クリニックでは、吐き気や嘔吐の原因を正確に診断し、それぞれの症状に合わせた適切な治療を行います。特に、脱水症状や重篤な病気のサインを見逃さないよう、詳細な問診と必要な検査を通じて、迅速な対応を心がけています。つらい吐き気や嘔吐でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
▶吐き気/嘔吐の原因
吐き気や嘔吐は、非常に多くの原因で起こります。原因を特定するためには、症状の現れ方や、他にどんな症状があるかなどを詳しく調べることが重要です。主な原因としては、以下のようなものが挙げられます。
| 消化器系の病気 |
|---|
| 【感染性胃腸炎】 ウイルス(ノロウイルス、ロタウイルスなど)や細菌(サルモネラ菌、O-157など)の感染により、吐き気、嘔吐、下痢、発熱などを伴います。 |
| 【急性胃炎・胃潰瘍】 食べ過ぎ、飲み過ぎ、ストレス、薬剤などが原因で胃の粘膜が炎症を起こし、吐き気や腹痛が生じます。 |
| 【虫垂炎】 いわゆる「盲腸」で、初期にみぞおちの不快感や吐き気、嘔吐を伴うことがあります。 |
| 【腸閉塞】 腸が詰まることで、激しい腹痛とともに嘔吐を繰り返します。 |
| 【胆石症・膵炎】 胆嚢や膵臓の病気でも、みぞおちから右わき腹の痛みとともに吐き気や嘔吐が見られることがあります。 |
| 脳の病気 |
| 【片頭痛】 激しい頭痛とともに吐き気を伴うことがあります。 |
| 【脳腫瘍・髄膜炎】 脳圧が上昇することで、吐き気を伴う頭痛や嘔吐が見られることがあります。 |
| 【メニエール病】 めまいとともに吐き気を伴うことがあります。 |
| 全身の病気やその他の原因 |
| 【薬の副作用】 一部の薬(抗がん剤、痛み止めなど)は、副作用で吐き気や嘔吐を引き起こすことがあります。 |
| 【乗り物酔い】 揺れや動きが平衡感覚を刺激し、吐き気を引き起こします。 |
| 【妊娠】 つわりとして、吐き気や嘔吐がみられます。 |
| 【ストレス・心因性】 精神的な要因で、吐き気や嘔吐が起こることがあります。 |
| 【高血糖(糖尿病性ケトアシドーシス)】 糖尿病の重症合併症で、強い吐き気や腹痛を伴うことがあります。 |
| 【熱中症】 体温調節機能が破綻することで、吐き気や嘔吐、めまいなどを伴います。 |
▶検査と治療
吐き気や嘔吐の治療は、その原因を特定し、適切な対処を行うことが重要です。
検査
症状や診察所見から、必要に応じて以下の検査を行います。
- 問診・身体診察: 吐き気や嘔吐の頻度、量、内容物、他にどのような症状があるかなどを詳しくお伺いし、お腹の状態などを確認します。
- 血液検査: 脱水や電解質バランスの異常、炎症の程度、肝臓や膵臓の機能、血糖値などを調べます。
- 尿検査: 脱水の程度や、他の病気のサインがないかを確認します。
- 腹部超音波検査(エコー): 肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、腸などの状態を画像で確認し、結石や炎症、腫瘍の有無などを調べます。
- 腹部X線検査(レントゲン): 腸閉塞の有無などを確認します。
- 感染症の迅速検査: 必要に応じて、ノロウイルスなどの迅速検査を行うことがあります。
治療
検査結果に基づき、患者さまの状態や原因疾患に合わせた治療を行います。
【薬物療法】
吐き気を抑える薬(制吐剤)、胃酸を抑える薬、整腸剤、抗生物質(細菌感染の場合)などを処方します。
【点滴療法】
吐き気や嘔吐がひどく、水分が摂れない場合や脱水症状が強い場合には、点滴で水分や栄養を補給します。
【対症療法と生活指導】
症状が落ち着くまでの食事指導(刺激の少ないもの、消化の良いものなど)、安静の指導、水分補給の重要性などについてアドバイスします。
【専門医療機関への紹介】
緊急性が高い病気(虫垂炎、腸閉塞、脳の病気など)や、より専門的な検査・治療が必要な場合は、速やかに地域の基幹病院や専門医療機関へご紹介し、連携して治療を進めます。
▶受診の目安
- 激しい嘔吐が止まらない、または意識が朦朧としている
- 水分が全く摂れない、尿の量が極端に少ないなど、脱水症状が疑われる
- 激しい腹痛を伴う
- 吐いたものに血液が混じっている(コーヒーのような色の場合も含む)
- 頭痛やめまい、高熱を伴う
- 胸の痛みや息苦しさを伴う
- 症状が長く続く(24時間以上)、または徐々に悪化している
- 持病(糖尿病、心臓病、腎臓病など)をお持ちの方
※本ページの内容は、みらいとクリニックの医師が監修しています。
