症状 / 全身
睡眠時無呼吸症候群
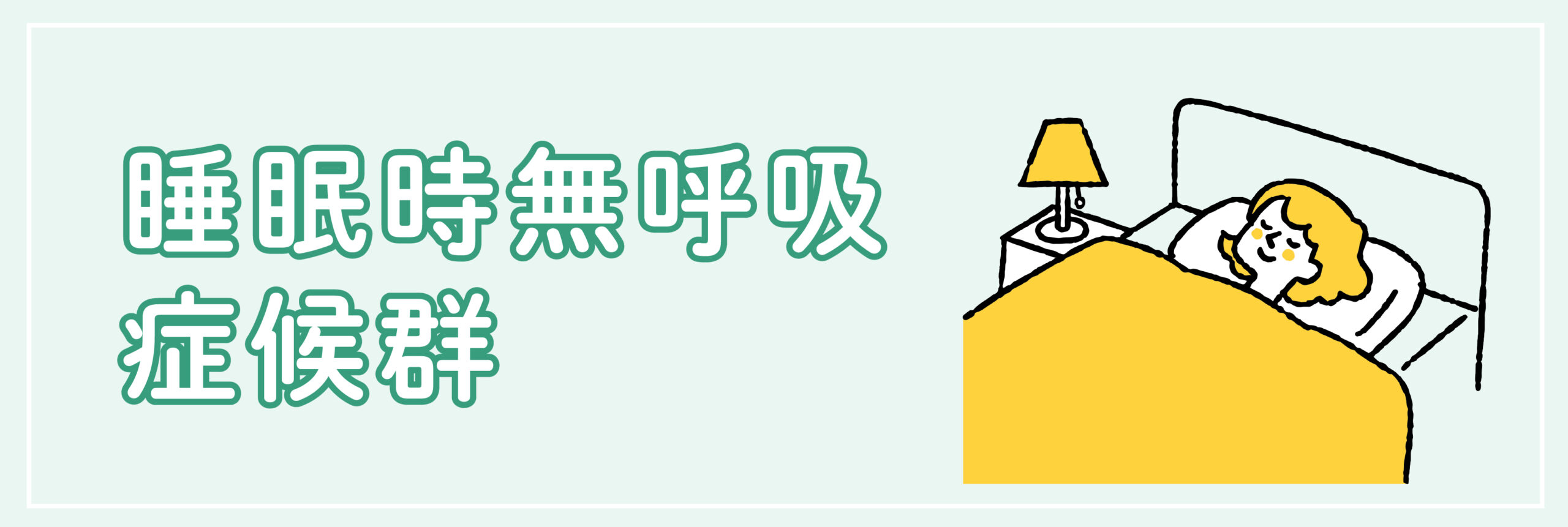
▶睡眠時無呼吸症候群について
「睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)」とは、寝ている間に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりを繰り返す病気です。多くの場合、大きないびきを伴い、本人は気づいていなくても、家族から指摘されて発覚することも少なくありません。呼吸が止まると、体に取り込まれる酸素の量が減り、脳が覚醒して呼吸を再開させようとします。これを一晩に何十回、何百回と繰り返すため、深い眠りが妨げられてしまうのです。
睡眠時無呼吸症候群を放置すると、日中の強い眠気や集中力の低下など、日常生活に支障をきたすだけでなく、高血圧、糖尿病、心臓病、脳卒中などの重篤な病気を引き起こすリスクが高まることが分かっています。当クリニックでは、睡眠時無呼吸症候群の検査から診断、治療までを一貫して行っております。気になる症状があれば、決して自己判断せず、お気軽にご相談ください。
▶睡眠時無呼吸症候群の原因
睡眠時無呼吸症候群にはいくつかのタイプがありますが、そのほとんどは「閉塞型睡眠時無呼吸症候群(OSAS)」と呼ばれるものです。これは、寝ている間に空気の通り道である上気道(のどや鼻の奥)が狭くなったり、完全に塞がったりすることで起こります。主な原因は以下の通りです。
| 【肥満】 首回りやのどに脂肪がつくことで、上気道が狭くなりやすくなります。肥満は最も一般的な原因の一つです。 |
| 【扁桃肥大・アデノイド肥大】 特に小児の場合に多く見られますが、大人でも扁桃腺やアデノイドが大きいと、上気道が狭まる原因になります。 |
| 【顎の形・舌の大きさ】 下顎が小さい、引っ込んでいる、舌が大きいといった骨格的な特徴も、上気道を狭くする要因となります。 |
| 【鼻の病気】 鼻炎や鼻中隔湾曲症(鼻の真ん中の仕切りが曲がっている状態)などにより鼻が詰まっていると、口呼吸になりやすく、睡眠中の呼吸が不安定になることがあります。 |
| 【加齢】 年齢とともに、のどや舌の筋肉が緩みやすくなるため、上気道が閉塞しやすくなります。 |
| 【アルコール・睡眠薬の服用】 これらは筋肉を弛緩させる作用があるため、のどの筋肉が緩み、上気道が閉塞しやすくなります。 |
| 【喫煙】喫煙はのどの粘膜の炎症を引き起こし、むくみによって気道を狭めることがあります。 |
▶検査と治療
睡眠時無呼吸症候群の診断と治療は、患者さまの症状や重症度に合わせて行われます。
検査
症状や診察所見から、必要に応じて以下の検査を行います。
- 問診: いびきの有無、日中の眠気やだるさ、起床時の頭痛など、症状について詳しくお伺いします。家族からの情報も重要です。
- 簡易検査(自宅で可能): ご自宅で手軽に行える検査です。センサーを指や鼻につけて寝るだけで、睡眠中の呼吸の状態や血液中の酸素濃度などを記録します。これにより、睡眠時無呼吸症候群の可能性や重症度がある程度分かります。
- 精密検査(PSG:ポリソムノグラフィー検査): 簡易検査で異常が見つかった場合や、より詳細な診断が必要な場合に検討します。通常は医療機関に一泊入院して行い、脳波、眼球運動、筋電図、心電図、呼吸の状態、血液中の酸素濃度など、多くの項目を同時に測定し、睡眠の質や呼吸の状態を詳細に分析します。
治療
診断の結果、睡眠時無呼吸症候群と診断された場合、その重症度や患者さまの状態に合わせて以下の治療を行います。
【CPAP(シーパップ)療法】
最も一般的な治療法です。睡眠中にマスクを装着し、専用の装置から空気を送り込むことで、狭くなった上気道を広げ、無呼吸を防ぎます。症状が中等度から重度の方に有効で、日中の眠気の改善や合併症のリスク軽減に大きな効果があります。
【マウスピース(口腔内装置)】
軽症から中等症の方に有効な場合があります。下顎を少し前に突き出すように固定することで、上気道を広げ、いびきや無呼吸を軽減します。歯科医院と連携して作製します。
【生活習慣の改善】
肥満がある場合は減量、アルコール摂取の制限、禁煙、規則正しい睡眠習慣の確立などが重要です。これらの改善は、病状の軽減に役立ちます。
【外科的治療】
扁桃肥大など、上気道を塞いでいる原因が明確な場合に、手術を検討することがあります。
▶受診の目安
- 大きないびきをかく、家族からいびきを指摘される
- 睡眠中に呼吸が止まっていると指摘される
- 日中に強い眠気を感じる、居眠りをしてしまう
- 起床時に頭痛がする、口が渇いている
- 夜中に何度も目が覚める、トイレに行く回数が多い
- 疲れが取れない、集中力がない
- 高血圧、糖尿病、肥満を指摘されている
※本ページの内容は、みらいとクリニックの医師が監修しています。
