症状 / 全身
高血圧
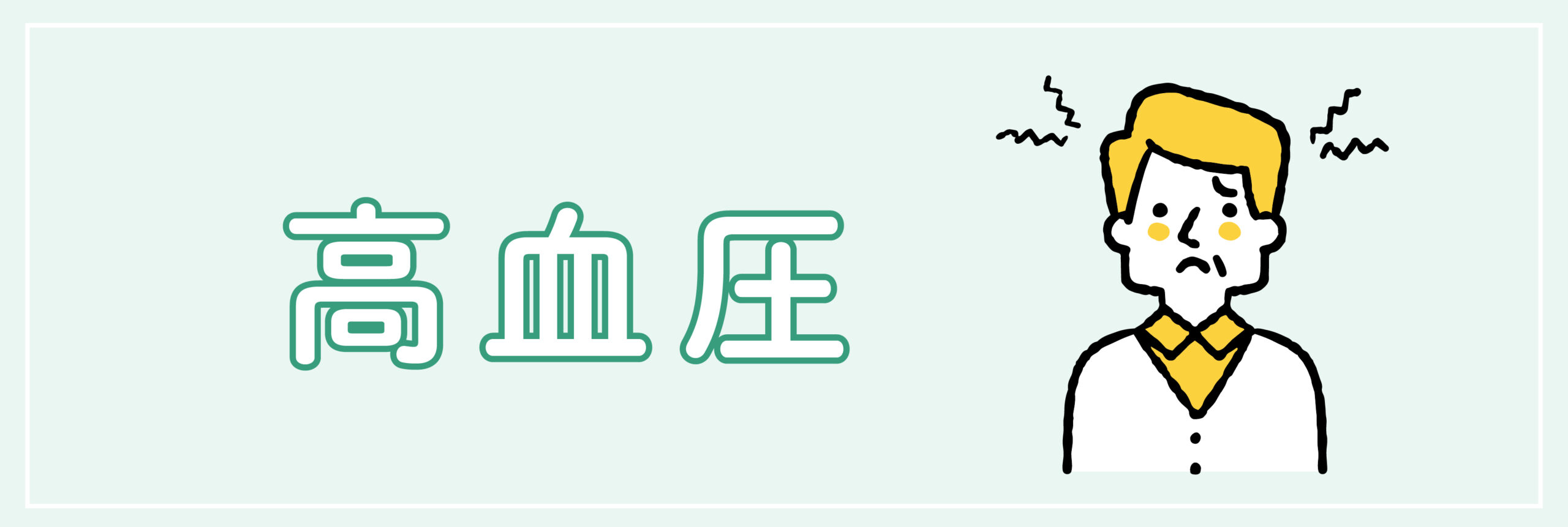
▶高血圧について
高血圧とは、血圧が正常範囲よりも高い状態が慢性的に続く病気です。血圧とは、心臓から送り出された血液が血管の壁を押す力のことです。収縮期血圧(最高血圧)が140mmHg以上、または拡張期血圧(最低血圧)が90mmHg以上の場合を高血圧と診断されます(診察室で測定した場合)。また自宅で測る家庭血圧の場合は、診察室で測定した場合よりも低い基準が用いられます。
高血圧は、ほとんどの場合、自覚症状がありません。そのため「サイレントキラー(沈黙の殺人者)」とも呼ばれ、気づかないうちに病気が進行してしまうことが問題となります。高血圧の状態が長く続くと、血管に常に大きな負担がかかり、血管の壁が硬くなる「動脈硬化」を進行させます。 動脈硬化が進むと、心臓病(狭心症、心筋梗塞、心不全など)や脳卒中(脳出血、脳梗塞など)、腎臓病(慢性腎臓病)など、命に関わるような重大な病気を引き起こすリスクが非常に高まります。
当クリニックでは、高血圧の早期発見と、一人ひとりの患者さまに合わせた適切な治療を通じて、これらの合併症を予防し、健康な生活を長く送っていただけるようサポートしています。健康診断で血圧が高いと指摘された方や、血圧が気になる方は、どうぞお気軽にご相談ください。
▶高血圧の原因
| 本態性高血圧症(ほとんどの場合がこれに該当) 高血圧患者さまの約90%が、この「本態性高血圧症」に当てはまります。特定の原因が一つだけあるわけではなく、遺伝的な体質に、以下のような生活習慣の要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。 |
|---|
| 【塩分の摂りすぎ】 塩分を摂りすぎると体内の水分が増え、血液量が増加したり、血管が収縮しやすくなったりして血圧が上がります。 |
| 【肥満】 肥満になると、脂肪細胞により、血圧を上昇させる物質が増えるだけでなく、血管の弾力性を保つ物質が減少することで動脈硬化が進みやすくなり、さらに血圧が上がりやすくなります。 |
| 【喫煙】 タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させ、動脈硬化を促進します。 |
| 【飲酒のしすぎ】 過度な飲酒は一時的に血圧を上昇させ、長期的にも高血圧のリスクを高めます。 |
| 【運動不足】 運動不足は肥満につながるだけでなく、血管の弾力性が失われる原因にもなります。 |
| 【ストレス】 ストレスは交感神経を刺激し、一時的に血圧を上昇させることがあります。慢性的なストレスは高血圧につながる可能性も指摘されています。 |
| 【睡眠不足】 慢性的な睡眠不足も血圧を上昇させる要因となりえます。 |
| 【加齢】 年齢を重ねるとともに血管の弾力性が失われ、動脈硬化が進みやすくなるため、血圧は自然と高くなる傾向があります。 |
| 二次性高血圧症(病気が原因となる高血圧) 高血圧患者さんの約5~10%は、何らかの病気が原因で高血圧になっている「二次性高血圧症」です。この場合、原因となっている病気を治療することで、高血圧も改善することが期待できます。 |
| 【腎臓の病気】 腎臓は血圧の調整に関わるため、腎炎や腎動脈狭窄症など腎臓の病気があると高血圧になります。 |
| 【内分泌の病気】 副腎や甲状腺の病気など、特定のホルモンが過剰に分泌されることで高血圧になることがあります。 |
| 【睡眠時無呼吸症候群】 睡眠中に呼吸が止まることで、体内の酸素不足が起こり、血圧が上昇しやすくなります。 |
| 【薬剤の影響】 一部の薬剤(ステロイド、痛み止めなど)の副作用で血圧が上がることがあります。 |
▶検査と治療
高血圧の治療は、まずその原因を特定し、患者さまの状態やリスクに応じた方法を選択することが重要です。
検査
高血圧の診断と、合併症の有無、原因の特定のために、以下の検査を行います。
- 血圧測定:ご自宅での血圧測定(家庭血圧)の結果も非常に重要です。診察室での血圧と合わせて総合的に評価します。
- 血液検査:コレステロールや血糖値(糖尿病の有無)、肝機能、腎機能、尿酸値などを確認し、合併症のリスクや他の病気の有無を調べます。
- 尿検査:尿中にタンパクや糖が出ていないか、腎臓への影響がないかなどを確認します。
- 心電図検査:不整脈の有無や、高血圧によって心臓に負担がかかっていないか(心肥大など)を調べます。
- 胸部X線検査(レントゲン):必要に応じて心臓の大きさや肺の状態を確認します。
- 血管検査(動脈硬化検査):脈波伝播速度(PWV)や足関節上腕血圧比(ABI)などで、血管の硬さや詰まり具合を評価し、動脈硬化の進行度を確認します。
治療
検査結果と患者さまの状態に基づいて、治療方針を決定します。
【生活習慣の改善】
全ての高血圧治療の基本となります。塩分制限(1日6g未満が目標)、野菜や果物を多く摂るバランスの良い食事、適度な運動、減量、禁煙、節酒、ストレスの軽減、十分な睡眠などが含まれます。
【薬物療法】
生活習慣の改善だけでは血圧が十分に下がらない場合や、血圧が非常に高い場合、合併症のリスクが高い場合は、降圧薬(血圧を下げる薬)を服用します。患者さまの状態や合併症の有無に合わせて、適切な種類の薬を選択します。(カルシウム拮抗薬、ACE阻害薬/ARB、利尿薬、β遮断薬 など)
【原因疾患の治療】
二次性高血圧症と診断された場合は、原因となっている病気(腎臓病、内分泌疾患、睡眠時無呼吸症候群など)の治療を優先します。
【定期的な受診と検査】
血圧を安定させ、合併症の発生や悪化を防ぐために、定期的な受診と検査を通じて血圧の管理や体の状態のチェックを継続します。
▶受診の目安
- 健康診断で血圧が高いと指摘された方
- ご自宅で測る血圧が、基準値(収縮期135mmHg以上、拡張期85mmHg以上)より高い場合
- 親や兄弟に高血圧、心臓病、脳卒中の方がおり、心配を抱えている
- 頭重感、めまい、肩こり、動悸など、何となく血圧が高いかもしれないと感じる症状がある
- 今まで高血圧でなかったのに、急に血圧が高くなった
- すでに高血圧と診断されているが、なかなか血圧が下がらない、または血圧の薬について相談したい
※本ページの内容は、みらいとクリニックの医師が監修しています。
