症状 / 全身
脂質異常症
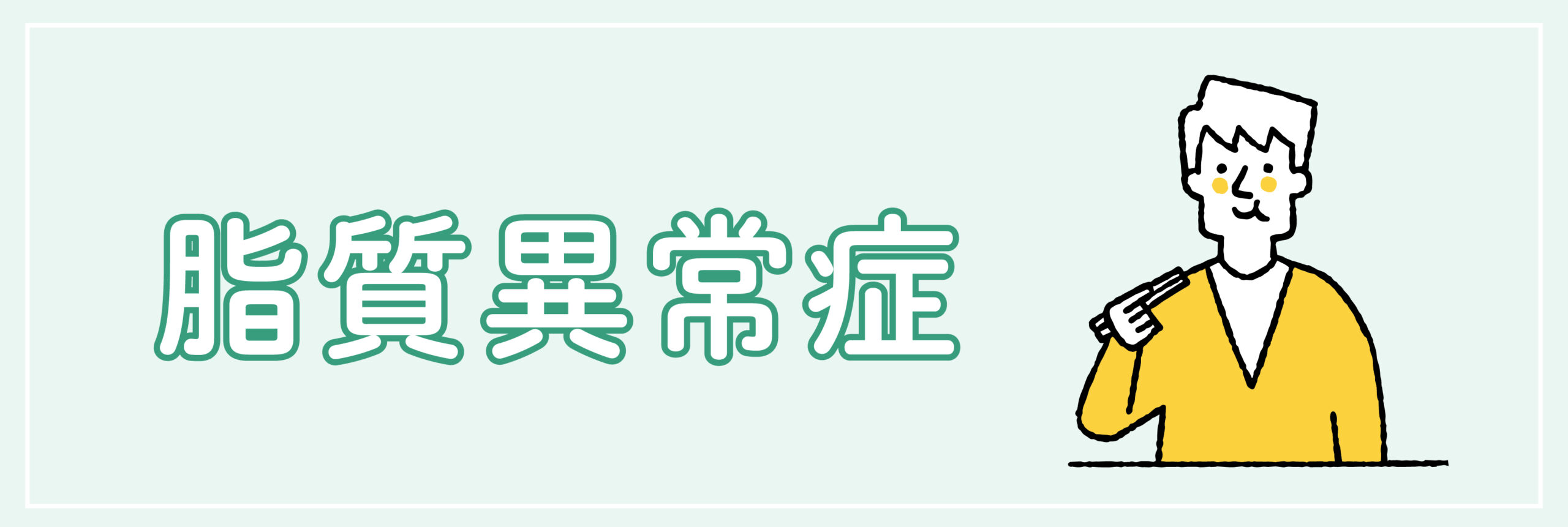
▶脂質異常症について
脂質異常症とは、血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪)の量が、基準値から外れてしまう病気です。以前は「高脂血症」と呼ばれていましたが、コレステロールの中でも体に良いとされるHDLコレステロールが低い場合も病気として扱われるため、現在は「脂質異常症」という名称が使われています。
脂質異常症は、高血圧や糖尿病と同様に、ほとんど自覚症状がありません。 しかし、放置すると、血管の壁に余分な脂質がたまり、血管が硬くなったり狭くなったりする「動脈硬化」を進行させてしまいます。 動脈硬化は、心臓病(狭心症、心筋梗塞など)や脳卒中(脳出血、脳梗塞など)といった、命に関わる重大な病気の主な原因となります。
当クリニックでは、脂質異常症の早期発見と、一人ひとりの患者さまに合わせた適切な治療を通じて、動脈硬化の進行を抑え、これらの合併症を予防し、健康な生活を長く送っていただけるようサポートしています。健康診断で脂質の値の異常を指摘された方や、血縁者に心臓病や脳卒中の方がいるなど、脂質が気になる方は、どうぞお気軽にご相談ください。
| 脂質異常症の主なタイプと基準値(空腹時採血) | |
|---|---|
| LDLコレステロール(悪玉) | 基準値(mg/dL)60~119 脂質異常症の診断基準(mg/dL)140以上 |
| HDLコレステロール(善玉) | 基準値(mg/dL)40~80 脂質異常症の診断基準(mg/dL)40未満 |
| 中性脂肪 | 基準値(mg/dL)30~149 脂質異常症の診断基準(mg/dL)150以上 |
▶脂質異常症の原因
脂質異常症の主な原因は、遺伝的な体質と、日々の生活習慣が複雑に絡み合っていると考えられています。
| 生活習慣による要因(最も多い原因) |
|---|
| 【食生活の乱れ】 飽和脂肪酸やコレステロールの摂りすぎ: 肉の脂身、バター、卵黄、内臓類などに多く含まれ、LDLコレステロールを増やしやすいです。 |
| 【糖質やアルコールの摂りすぎ】 中性脂肪の増加につながります。 |
| 【食物繊維の不足】 食物繊維はコレステロールの吸収を抑える働きがあります。 |
| 【運動不足】 運動不足は、HDLコレステロールの減少や中性脂肪の増加につながりやすいです。 |
| 【肥満】 特に内臓脂肪の蓄積は、脂質代謝に悪影響を与え、LDLコレステロールや中性脂肪の増加、HDLコレステロールの減少を招きます。 |
| 【喫煙】 喫煙はHDLコレステロールを減らし、LDLコレステロールを酸化させ、動脈硬化を促進します。 |
| 【過度な飲酒】 中性脂肪の増加に直結します。 |
| その他の要因 |
| 【遺伝的要因】 家族に脂質異常症や動脈硬化性の病気(心筋梗塞、脳梗塞など)の人がいる場合、体質的に脂質異常症になりやすいことがあります。 |
| 【他の病気】 糖尿病、甲状腺機能低下症、腎臓病、肝臓病、膵臓の病気など、一部の病気が原因で脂質異常症になることがあります。 |
| 【薬剤の副作用】 一部の薬剤(ステロイド、β遮断薬、経口避妊薬など)の副作用で脂質の値が変動することがあります。 |
| 【加齢】 年齢を重ねるとともに、脂質の代謝機能が低下し、脂質異常症になりやすくなります。 |
▶検査と治療
脂質異常症の治療は、まずその原因を特定し、患者さまの状態や合併症のリスクに応じた方法を選択することが重要です。
検査
脂質異常症の診断と、合併症の有無、原因の特定のために、以下の検査を行います。
- 血液検査(脂質検査):空腹時に採血を行い、LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪の値を測定します。診断にはこれらの値が不可欠です。
- 血液検査(その他の項目):血糖値(糖尿病の有無)、肝機能、腎機能、甲状腺機能などを確認し、他の病気が脂質異常症の原因となっていないか、また合併症がないかなどを調べます。
- 血圧測定:高血圧を合併していることが多いので、血圧を測定します。
- 尿検査:腎臓への影響がないかなどを確認します。
- 心電図検査:不整脈の有無や、心臓への負担がないかなどを調べます。
- 血管検査(動脈硬化検査):脈波伝播速度(PWV)や頸動脈エコーなどで、血管の硬さや詰まり具合を評価し、動脈硬化の進行度を確認します。
治療
検査結果と患者さまの状態、動脈硬化性疾患のリスクに基づいて、治療方針を決定します。
【生活習慣の改善】
最も重要で、全ての脂質異常症治療の基本となります。
【食生活の見直し】
飽和脂肪酸(肉の脂身、バターなど)やコレステロール(卵黄、魚卵など)の摂取を控える、食物繊維(野菜、海藻、きのこなど)を積極的に摂る、魚(特に青魚)や植物油(オリーブオイルなど)から良質な脂質を摂る、糖質やアルコールの過剰摂取を控えるなど食生活のポイントをアドバイスさせていただきます。
【適度な運動】
ウォーキングなど、無理のない範囲で毎日続けられる有酸素運動が効果的です。
【減量】
肥満がある場合は、適正体重を目指すことで脂質の値が改善することが多いです。
【禁煙・節酒】
喫煙は直ちにやめ、飲酒は適量を心がけます。
【ストレス管理】
ストレスも脂質代謝に影響を与えることがあるため、リラックスする時間を作ることも大切です。
【薬物療法】
生活習慣の改善だけでは脂質の値が十分に下がらない場合や、動脈硬化性疾患のリスクが高い場合は、脂質を下げる薬(脂質降下薬)を服用します。患者さまの脂質のタイプや合併症の有無に合わせて、適切な種類の薬を選択します。(スタチン系薬剤(LDLコレステロール低下)、フィブラート系薬剤(中性脂肪低下)、小腸コレステロールトランスポーター阻害薬、EPA製剤(中性脂肪低下) など)
【原因疾患の治療】
他の病気(糖尿病、甲状腺機能低下症など)が原因で脂質異常症になっている場合は、その病気の治療を優先します。
【定期的な受診と検査】
脂質の値を安定させ、動脈硬化の進行や合併症の発生を防ぐために、定期的な受診と検査を通じて脂質の管理や体の状態のチェックを継続します。
▶受診の目安
- 健康診断でLDLコレステロール、中性脂肪が高い、またはHDLコレステロールが低いと指摘された方
- 家族に脂質異常症、心臓病(狭心症、心筋梗塞など)、脳卒中の方がおり、心配を抱えている方
- 高血圧や糖尿病をすでに診断されている方
- 肥満気味である、または食生活が乱れがちだと自覚している方
- 最近、体重が増えた、運動不足だと感じる方
- 生活習慣病のリスクについて相談したい方
※本ページの内容は、みらいとクリニックの医師が監修しています。
