症状 / 全身
肥満症
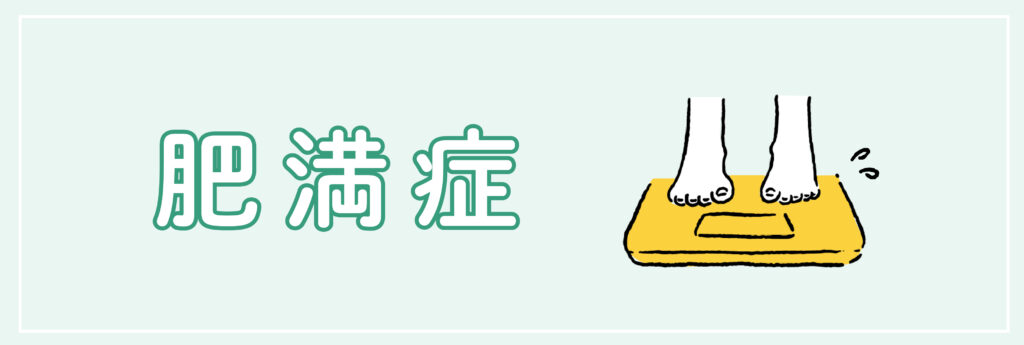
▶肥満症について
肥満症とは、単に体重が多いだけでなく、体脂肪が過剰に蓄積し、それによって健康上の問題が生じている、または将来的に問題が生じるリスクが高い状態を指します。体重の指標としてよく使われるのが「BMI(Body Mass Index)」です。
BMI = 体重(kg)÷ 身長(m)÷ 身長(m)
一般的に、BMIが25以上を肥満といい、その中でも高血圧、脂質異常症、糖尿病といった生活習慣病を合併している、または合併するリスクが高い場合に「肥満症」と診断されます。
肥満症は、見た目の問題だけでなく、高血圧、脂質異常症、糖尿病といったさまざまな生活習慣病、さらには睡眠時無呼吸症候群、脂肪肝、痛風、変形性関節症、一部のがんなど、多くの病気を引き起こしたり悪化させたりすることが分かっています。しかし、肥満症は適切な治療と生活習慣の改善で、これらのリスクを大きく減らすことができる病気です。
「健康診断で肥満を指摘された」「体重がなかなか減らない」「お腹周りが気になる」などのお悩みはありませんか? 当クリニックでは、肥満症でお悩みの方に、一人ひとりの状態に合わせた適切な診断と治療を通じて、健康的な体重管理をサポートしています。どうぞお気軽にご相談ください。
▶肥満症の原因
肥満症の主な原因は、摂取するエネルギー(カロリー)が、消費するエネルギーを上回る状態が続くことです。しかし、その背景にはさまざまな要因が複雑に絡み合っています。
| 過食・食生活の乱れ |
|---|
| 【高カロリーな食事】 脂質や糖質が多い食事(揚げ物、菓子類、清涼飲料水、加工食品など)の過剰な摂取。 |
| 【早食い】 満腹感を感じる前に食べ過ぎてしまう傾向。 |
| 【不規則な食事時間】 朝食を抜いたり、夜遅くに食事をしたりすると、体脂肪が蓄積しやすくなります。 |
| 【間食のしすぎ】 無意識のうちに間食が増え、総カロリーが増加。 |
| 運動不足 |
| 日常生活での活動量が少なく、エネルギー消費が少ないと、余ったエネルギーが体脂肪として蓄積されます。車での移動が多い、座り仕事中心、運動習慣がないなどが挙げられます。 |
| 遺伝的要因 |
| 肥満になりやすい体質は、遺伝的な影響も大きいとされています。家族に肥満の方が多い場合、その傾向は高まります。 |
| 基礎代謝の低下 |
| 加齢とともに基礎代謝(生命維持に必要なエネルギー消費量)が低下するため、若い頃と同じような食生活を続けていると太りやすくなります。 |
| 睡眠不足 |
| 睡眠不足は食欲を増進させるホルモンが増え、食欲を抑えるホルモンが減ると言われており、肥満につながることがあります。 |
| ストレス |
| ストレスが原因で過食に走ったり、活動量が減ったりして体重が増えることがあります。 |
| 特定の病気や薬の影響 |
| 【内分泌疾患】 甲状腺機能低下症など、ホルモンの異常が原因で代謝が低下し、体重が増加することがあります。 |
| 【薬剤の副作用】 一部の薬剤(ステロイド、抗うつ薬、糖尿病治療薬の一部など)が体重増加の副作用を持つことがあります。 |
▶検査と治療
肥満症の治療は、単に体重を減らすだけでなく、生活習慣病の改善や合併症の予防を目的とします。患者さま一人ひとりの状態やライフスタイルに合わせて、無理なく続けられる方法を一緒に考えていきます。
検査
肥満症の診断と、合併している病気や合併症のリスクを評価するために、以下の検査を行います。
- 身体測定:身長、体重、BMIの測定。また、腹囲測定で内臓脂肪の蓄積度を評価します。
- 血液検査:血糖値(糖尿病の有無)、HbA1c、コレステロールや中性脂肪(脂質異常症の有無)、肝機能(脂肪肝の有無)、腎機能、尿酸値(高尿酸血症・痛風の有無)、甲状腺機能などを確認し、合併症や他の病気の有無を調べます。
- 血圧測定:高血圧を合併していることが多いので、血圧を測定します。
- 尿検査:尿糖や尿蛋白の有無を確認し、糖尿病や腎臓への影響がないか調べます。
- 超音波検査(エコー):脂肪肝の有無などを確認するために、お腹の超音波検査を行うことがあります。
- 睡眠検査(必要に応じて):睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合、簡易的な睡眠検査を行うことがあります。
治療
検査結果と患者さまの状態、合併症の有無、減量の目標などに基づいて、治療方針を決定します。
【食事療法】
摂取カロリーを適切に管理し、栄養バランスの取れた食事を心がけます。
- 具体的なアドバイス: 食べ過ぎない工夫、早食いの改善、食物繊維の多い食品の摂取、脂質や糖質の摂りすぎに注意することなど、無理なく続けられる具体的な食事内容や食べ方について指導します。
- 管理栄養士との連携: 必要に応じて、専門の管理栄養士による詳細な栄養指導を行うこともあります。
【運動療法】
エネルギー消費を増やし、基礎代謝を高めるために、適度な運動を取り入れます。
- 具体的なアドバイス: ウォーキングや軽いジョギング、水泳など、毎日続けられる有酸素運動を中心に、筋力トレーニングも組み合わせることを推奨します。個人の体力や健康状態に合わせて、無理のない範囲で運動プランを立てます。
【行動療法】
肥満につながる生活習慣や行動パターンを見直し、改善するためのサポートを行います。食行動の記録、ストレスへの対処法、睡眠習慣の改善など、多角的にアプローチします。
【薬物療法】
食事療法や運動療法だけでは十分な効果が得られない場合や、高度肥満で合併症のリスクが高い場合に、医師の判断で肥満症治療薬を検討することがあります。
【定期的な受診と検査】
体重や体脂肪の変化、血糖値、血圧、脂質などの数値を定期的にチェックし、治療の効果を確認しながら、必要に応じて治療方針を調整していきます。合併症の早期発見と管理も同時に行います。
【専門医療機関への紹介】
高度な肥満症で専門的な治療(減量手術など)が必要な場合や、他の専門的な疾患が強く疑われる場合は、連携する専門医療機関へご紹介します。
▶受診の目安
- BMIが25以上で、肥満を指摘された方
- BMIが25未満でも、お腹周り(腹囲)が気になる方(男性85cm以上、女性90cm以上が目安)
- 肥満に加えて、高血圧、脂質異常症、糖尿病のいずれかを指摘されている、またはその予備群である方
- 家族に肥満症や生活習慣病の方がおり、心配を抱えている方
- 体重が増えてから、いびきがひどくなった、日中の眠気が強くなった(睡眠時無呼吸症候群の可能性)
- 健診で肝機能の異常を指摘された(脂肪肝の可能性)
- 関節の痛み(特に膝や股関節、腰)が気になる
- ダイエットを試してもなかなか体重が減らない、またはリバウンドしてしまう
- ご自身の健康的な体重について相談したい方
※本ページの内容は、みらいとクリニックの医師が監修しています。
